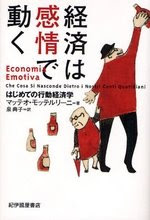著者:池上俊一 出版社;講談社 発行年:1992年 評価:☆☆☆☆☆
著者:池上俊一 出版社;講談社 発行年:1992年 評価:☆☆☆☆☆魔女が「増加」したとされる中世末期から近世末期にかけて、同時進行的に「聖女」の数も増加した。活版印刷の発展は聖書を普及させるとともに「悪魔学」も普及させ、その結果、「魔女狩り」が行われた地域ではステレオタイプの自白がみられることを著者は指摘する。さらに絶対王政の維持に魔女狩りが貢献した面があることも。農村内部がそれまでのコミュニティから格差拡大の時代を迎え、その不安を維持するために魔女狩りが用いられたとも主張する。そしてルネサンス、宗教改革、科学革命が進行する中で「選択肢」がシンプルになる中でその「枠」におさまりきれないものがすべて「魔女」(異端)として切り捨てられるようになった…という説が紹介される。そして中世後半に「母性」を中心とした「聖女」も対の概念としてうみだされてくる。家庭の中に「女性の空間」、アウトサイダーの女性は魔女として排斥されて外部は「男性の空間」となり、近代以降の女性は内、男性は外という区分けがこの魔女と聖女の中にみてとれるというわけだ。近代以前にこうした動きがあってこそ産業機械は男性が動かし、家内制手工業が女性が主に担うといったすみわけの「イデオロギー」がでてきたとも考えられる。ただこうした見方もステレオタイプの一つで著者は女性中心のギルドや女性が権力を握った例も紹介し、一面的な「考え」ですべてを切り落とすようなことはしないように…といった配慮が感じられる構成となっている。17世紀以降に魔女狩りが消滅した理由として著者はデカルトの近代合理主義を1つの「例」としてあげるが、その一方でこうした近代以前の魔女狩りが残した遺産、そしてその遺産を「輸入」した日本にも(おそらくは)一種の「考え方の偏り」を見出しているのだろう。ヨーロッパの歴史というとなんだか関係ないような気もしていたのだが、最後まで読んでいくと最終的には近代以降の日本の日常生活にも魔女と聖女のこの微妙な「区分け」の文化はしっかり潜んでいることがわかる。特に男性に「魔性の女」などといった表現にその名残があるようにも思えるのだが。