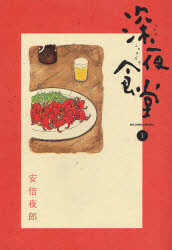著者;榊原英資 出版社;文藝春秋社 発行年;2008年 評価:☆☆☆☆
「産業革命」の前提として農業革命で生産効率が著しく上昇した結果、工場労働者が農村から供給される地盤が整備されていたことを知る人は案外少ない。しかし元大蔵省の「為替」を知り尽くしたエリートはいとも簡単に農業革命をさらっと説明してしまい、しかも単一商品栽培によるコストの低下と大英帝国の繁栄を数行で適確に表現してしまう。
映画「エリザベス~ゴールデンエイジ~」では弱小の大英帝国艦隊が無敵艦隊を迎え撃つシーンがやや悲壮に描写されていたが、著者の視線は局所的な海戦ではなく、
スペインやポルトガルの収奪的な植民地経営と英国とオランダの産業育成的な植民地経営を比較して長期的視点で大英帝国の繁栄をとらえなおす。
アメリカ北部においても農業や牧畜を中心とする産業を育成し、戦略的な植民地支配を行った。マレーシアにおけるゴムなどは特殊な例(またはインドにおける綿花など)だがあとはほとんど農産物。つまり「食」に関することだ。世界経済の「食」の市場を制圧することで大英帝国の覇権が確立されていったことがまず論証もしくは紹介される。
その後アメリカは米英戦争を経て独立。ヨーロッパとの貿易がとだえたことから国内の工業生産が発達するとともに、農業も小麦を中心に飛躍的に生産能力を向上させていき、ポスト大英帝国の土台を築いていく。大量生産・大量消費のまるで工業的な農業生産方法によって。さらに本書は食文化が栄えた絶対王政の時期のフランス・ブルボン王朝に嫁いできたイタリアのメディチ家の二人(カトリーヌ、マリー)、さらにルイ13世が迎えたフェリペ3世の娘、ルイ14世が迎えたフェリペ4世の娘、さらにオーストリアの王妃マリー・アントワネット、ルイ15世の迎えたポーランドのマリー・レクチンスキーとフランスにもたらされたイタリア、スペイン、オーストリア、ポーランドの食文化の輸入を指摘し、ワインからシャンパンが生まれた歴史を解説してくれる。
そしてフランス革命が貴族の料理を一般市民に拡大して現在にいたるわけだ。
ガストロノミー(美食学)の始まりである。さらに中国の食文化、オスマン帝国、インド、東南アジアと解説され、テーマは食の文化では歴史が古いアジアがなぜヨーロッパに侵略されたのかに移っていく。イスラム国家は商人のための国家というこれまで知らなかった解説をこの本で知り、ユダヤ商人やレバノン商人などもイスラム商人と行動をともにし、それを十字軍が破壊していったという見方を知る。そして東方貿易によってトマト、トウガラシなどがアメリカ大陸からヨーロッパに輸入されていく。ジャガイモもアンデス山脈からヨーロッパに輸入され現在の食文化を構築していく…。
わづかに200ページちょっとの文庫本だが内容は極めて濃く、しかもそのいずれもが経済に結び付いていくという構成が魅力的だ。著者の博学さと世界史の流れが一望できる点で素晴らしい一冊といえる。歴史的資料などをかなり参照して執筆されたことは巻末の参考資料の多さが物語る。グルメではなくとも読んでいて思わず内容に引き込まれていく
文庫本の中の名作。
 著者:ジョナサン・ワイナー 出版社:早川書房 発行年:1995年 評価:☆☆☆☆☆
著者:ジョナサン・ワイナー 出版社:早川書房 発行年:1995年 評価:☆☆☆☆☆